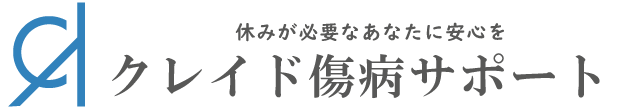【傷病手当金】受診時の注意点:病院・医師が証明してくれないリスクを減らすためにできること
以下記事にて、傷病手当金申請書の4ページ目「療養担当者記入用」(以下、申請書の医師証明)にて労務不能であることを証明してくれない事態になると大変であることをご説明いたしました。
傷病手当金の書類を書いてくれない!(病院編)
今回は、そのような事態にならないよう、病院を受診する際に注意すべき点の記事になります。
なお、本記事は精神疾患で、その病院での受診が初めて/数回目の場合を想定して書いております。
安心できる記載内容の診断書を書いてもらおう
まず、申請書の医師証明については既に過ぎた期間分しかもらえないという特徴があります。例えば、11月1日~11月30日分を証明してもらえるのは、12月になってからです。
そして、12月になって改めてお願いしたら、医師としては労務不能とまでは言えない、または判断できないから証明できないという答えが返ってくる。
これは、実は結構あるパターンです。そして、上記の状態になってしまうと、11月分についての受給は極めて困難になってしまいます。
これを防ぐために、診断書を書いてもらうのはとても有効な手段です。
申請書の医師証明と違って、診断書は未来に向かって書いてもらえます。また、書面で医師の考えを確認し保存できるため、精神面でもプラスになります。
例えば、「本日から〇〇日まで労務不能のため、自宅療養を要する」という記載の診断書が発行されていればどうでしょうか。ケガやインフルエンザ等客観的にデータで治癒が分かる傷病ならともかく、精神疾患において「想定より早く良くなったから証明できない」と判断されることは普通は考えられないので、かなりの安心材料になります。
診断書の料金は別途かかってしまいますが(病院により異なるが2,000円~4,000円程度が多い)、いざ傷病手当金が受給できないとなると大変なので、一種の保険として診断書を確保するのはおすすめです。通院も長くて医師との信頼関係があれば別ですが、特に最初のうちは診断書の記載を依頼されることを強く推奨いたします。
もし、退職も決まっているようでしたら退職日(もしくは退職日以降)まで労務不能の診断書発行も推奨しております。
離職後の継続受給を望まれる場合、労務不能期間に1日も空白があってはいけないので事前確認用に有効です。
また、退職日までの診断書があることで客観的に傷病による離職であることが分かり、健康保険上、雇用保険上で有利になる場合があります。
そして、「労務不能」「休職」「自宅療養」など客観的に働けないと分かる文言をいくらお願いしても書いてもらえないようであれば、申請書の医師証明についても期待できませんので、転院も検討しましょう。診断書の期間内に転院すれば、1日も空白なく傷病手当金の受給が継続できます(初診日以降の分しか証明してもらえないので、初回の場合はすみやかに検討しましょう)。
医師も人間なので、要望をはっきり言おう
受診の際に、以下の点についてはっきり伝えておくと良いでしょう。
・精神的にしんどく、働けない/働くのが難しい
・長期的な療養をしたいと考えている
・傷病手当金の受給を考えている(診断書をもらうなら省略も可。医師側から聞いてくれる場合も多いです)
医師も人間なので、コミュニケーションが必要です。
「弱みを見せるのが恥ずかしい」「厚かましいと思われないか」「否定されたらどうしよう」などと、特に弱っている時は思ってしまうかも知れませんが、仕事を頑張った結果患ってしまったあなたが悪いはずがない。安心して療養できる環境を得るために、医師にしっかり伝えましょう。
それでも不安なやりとりになったり、思うような診断書が得られない場合は転院も検討しましょう。何度も言いますが医師も人間なので、その個人の考えや患者との相性というものがあります。
転院したら、それまでが嘘のようにすんなりいくというのもよくある話です。
まとめ
しっかり医師に伝えること、労務不能と客観的に分かる診断書をあらかじめもらうことが重要ということになります。ただ、精神疾患以外の場合あてはまらない場合も出てくるので注意が必要です。
弊所にご相談いただければより具体的かつ広い範囲でアドバイスができると思いますので、ぜひご相談いただければと思います。
ご連絡、お待ちしております!
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健